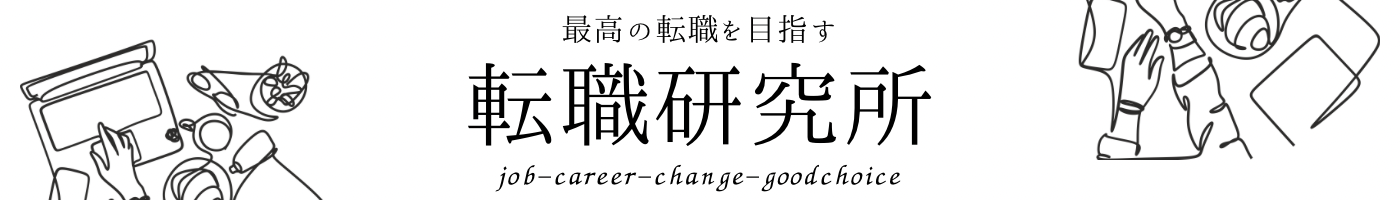金価格の上昇が続く

金(ゴールド)の価格がここ数年高騰を続けており、2025年3月には1トロイオンス(約31.1グラム)あたり3000ドルを超える史上最高値を記録しました。特に株式市場や債券市場と比べて規模が小さいながらも、金の存在感は無視できないほど拡大しています。中央銀行や機関投資家による積極的な買い増しが大きな要因とされ、特にロシアに対する金融制裁の影響が強まる中、中国が自国の資産防衛策として金を買い増す動機になっているとの見方があります。
論点
1. トランプリスクの中、安全資産と言われる金が買われている
近年の国際政治において、米国の政権交代やリーダーシップの変化は、金融市場に大きな影響を与えてきました。トランプ元大統領の政策は在任当時から常に世界経済へ強い波及力を持ち、為替や株式に乱高下をもたらしたといわれています。2025年現在、トランプ氏が再び政治的影響力を強める可能性があるという見方がくすぶっており、投資家にとっては「先行き不透明感」を増大させる要素の一つとなっています。こうした状況では、リスクヘッジのため「有事の金買い」が起こりやすいとされています。
金の安全資産としての性質
- 希少性:金は需給関係によって価値が保たれやすく、紙幣のように無制限に増刷することができません。
- 分割可能性:最小単位(粒状など)まで分割できるうえ、価値が失われにくい。
- 劣化しにくい:酸化や腐食に強く、長期間保管しても品質が変わりにくい。
こうした特性から、株式や債券よりも価格変動要因が異なり、経済や政治の混乱時に「資産の一部を金で保有する」選択肢を取る投資家が増えます。さらに、金の国際価格はドル建てで取引されることが多いため、米国経済や米ドルの信用リスクを回避しようとする動きが金需要を下支えする傾向にあります。
2. 株式市場の混乱が続く間は、金価格の上昇はしばらく続くのか
株式や債券市場が乱高下を続けると、投資家は安全資産へ資金を逃避させる傾向があります。特にここ数年、世界的にインフレ懸念が強まる中で、利上げと景気後退リスクとのせめぎ合いが続きました。新興国だけでなく先進国の中央銀行までもが、政策金利の引き上げと量的緩和の縮小を模索する局面にあり、金融市場には不安定要素が増えています。
需要サイドの動き
- 中央銀行による買い増し
ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の報告によれば、中央銀行による金の純購入量は2022年に約1136トンとされ、過去50年で最高水準に達したという推計も伝えられています。ロシア制裁やドル基軸通貨体制への不安感が背景にあり、中国をはじめロシアやインド、トルコなど、特定の国々が保有量を大幅に増やしているとされています。 - 機関投資家の関心
かつてはコモディティ(商品)として捉えられがちだった金ですが、ETFなどの金融商品を通じて容易に投資対象とできるようになったことで、各国の年金基金や投資ファンドが「ポートフォリオの分散先」として金を組み込みやすくなりました。株や債券と違う値動きをするため、全体のリスクを平準化できる効果が期待されます。
今後の見通し
- 地政学的リスクの増大
ロシアのウクライナ侵攻以降、欧米による制裁強化や中国の同盟関係への懸念など、地政学的リスクが高止まりしています。こうした不透明要因が続く限り、投資家はリスク回避先として金を選びやすいとみられます。 - ドルの信認問題と代替資産
金融制裁が進む中、ドルの信頼性を弱める材料が増えれば増えるほど、代替資産としての金への注目度が上がるでしょう。中国が金を積極的に買い増す動機の背景には「外貨準備の一部をドル以外で保有する狙いがある」とされており、ロシア制裁で得た教訓の一つだという見方もあります。
3. ロシア制裁と中国の金買い増し
ニュース本文にもあるように、ロシアに対する金融制裁はロシアの海外資産凍結などを含む厳しい内容が継続中です。一方、中国は「ロシアのウクライナ侵攻」に直接的に加担しているわけではないものの、ロシアとの関係を維持しつつ独自の経済圏を築こうという姿勢が見えます。その中で、国際決済システムSWIFT(国際銀行間通信協会)からの排除やドル決済の封じ込めリスクに備えるため、金を自国準備資産として積み増す動きが加速していると考えられています。
具体的な中国の金準備高の推移
- 中国人民銀行(中央銀行)が公表する公式準備高によれば、2022年末時点で約2,010トンとされています(ただし、公表が不透明とされる面もあり、実際の保有量はさらに多い可能性があると指摘されます)。
- この背景には、ドル以外の手段で資産価値を防衛しようという思惑があり、人民元の国際化戦略やデジタル人民元の普及策との連携も示唆されています。
4. 金の時価総額と今後のポテンシャル
記事中でも触れられているように、金の「地上在庫」は累計21万6265トンと推計され、現在価格をかけ合わせた規模は約3200兆円(約21兆ドル)にも上るといいます。これは世界の株式市場や債券市場に比べればまだ小さいものの、ここ25年ほどで20倍に拡大したのは非常に大きな伸びといえます。
- 株式や債券に対する補完的役割
金はインカムゲイン(利子・配当)がないため、長期的には債券や株式と異なるリスク・リターン特性を持ちますが、そのぶん「有事のときの価値の安定」に強みがあります。 - 売買高の拡大
店頭市場(OTC)や取引所に加えて、ETFなどの金融商品を合わせた金の1日平均売買高は2023年時点で3000億ドルを上回る規模に増加し、米国短期国債(T-Bills)の売買高を超え、S&P500種株価指数の売買高に迫る勢いです。
まとめ
足元の世界経済は、米国の利上げ方針やトランプ元大統領の政治的動向、さらにウクライナ情勢やロシア制裁の行方など、不透明感に包まれています。中国がドル資産を大幅に減らす可能性は低いものの、制裁リスクへの備えとして金の買い増しを続けることは十分考えられるでしょう。こうした動きは、国際金融システムへの信頼の揺らぎを映し出すものであり、投資家にとっては金が資産防衛の役割を担う存在として、ますます無視できない対象になっていくと考えられます。
また、株式市場の変動が続く間、金価格が急落するシナリオは見えにくいといえます。もちろん、金融引き締めの影響による世界的な景気後退や、米国での政治リスクが後退する場面がくれば、金に流れていた資金が再び株式や債券にシフトする可能性もあります。しかし、現時点ではトランプリスクを含む地政学的リスクが拭えず、ドル覇権体制に対する懸念も消え去ってはいません。そのため、当面は金への注目は続き、相場も高止まりする余地があるでしょう。
いずれにしても、アメリカの政治動向は世界の投資家にとって大きな意味を持ちます。米国内の政策や金融政策の方針は、グローバルマネーの流れを左右する決定要因になるからです。今後も金の価格を左右する材料として、米国がどのような経済運営・金融政策を取るのか、そして世界的な地政学的リスクがどう変化していくのかを注視していく必要があるでしょう。筆者としては、「どちらかが沈静化すれば金価格は落ち着くかもしれないが、いずれかの火種が燃え続ける限りは、金は堅調に推移する可能性が高い」と考えています。