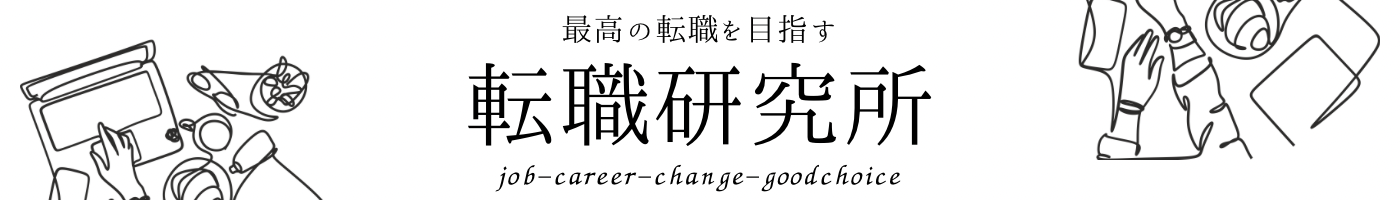転職活動では「なぜ落ちたのか?」が分からず悩むことがありますよね。40代で数多くの選考を経験してきた私も、当初は理由が掴めずもやもやする日々がありました。しかし、面接官の立場を想像し、自分の選考を振り返る中で、少しずつ「採用の現場ではこう見られているのか」というポイントが見えてきました。そこで本記事では、採用担当者の本音に迫り、選考基準のリアルなところをお伝えします。
書類選考の時点で落ちる理由、実はここ!

「面接までたどり着けない…」そんなとき、原因は年齢そのものより他にあるケースが多いと感じます。私自身、最初は年齢が高いから書類で落とされるのだと思い込んでいました。しかし実際には、希望する年収の高さや職歴の内容などで足切りされている場合が少なくありません。ある回答者も「年齢よりも希望年収や経験・能力の方が影響する」と指摘していますdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp。企業側から見ると、予算オーバーになりそうな人や、求めるスキルと関係ない経歴の人は、残念ながら書類の段階で優先度を下げざるを得ないのでしょう。
例えば私も、当初は前職の年収をベースに希望年収を高めに記載していましたが、それでは一向に書類通過率が上がりませんでした。希望年収欄をあえて空欄にするなど柔軟さを示したところ、面接に進める件数が増えました。また転職回数が多い場合は経歴に補足を入れてネガティブに映らないよう工夫しました。実際、40代で転職して年収アップできる人は4割程度というデータもありますlogmi.jp。書類選考ではこうした点を踏まえ、「この条件なら採用後もミスマッチにならない」と思ってもらえるような情報提供を心掛けることが重要です。
面接官が重視する「共感力」と「空気の読め方」
書類を突破して面接に臨んだら、今度は人間性の評価が鍵になります。特に私が痛感したのは、面接官が「共感力」と「空気を読む力」を非常に重視しているということです。どんなにスキルや経験が豊富でも、一方的に喋るばかりで相手の話に共感を示さなかったり、質問の意図とズレた回答をし続けたりすれば、高評価は望めません。
実際、企業が採用時に求める資質として、コミュニケーション能力が16年連続で第1位に挙がっているという調査結果がありますsaiyo.employment.en-japan.com。コミュニケーション能力とは単に話し上手ということではなく、相手の気持ちをくみ取ったり、場の雰囲気に合わせて適切に振る舞ったりできる力です。面接という緊張感のある場でも、相槌を打って相手の話に共感し、質問の背景を読み取りながら的確に答える姿勢が求められます。
私も最初の頃は、自分の伝えたいことばかり必死にアピールしてしまい、面接官の表情の変化に気づかないことがありました。ある質問に長々と答えすぎたせいで面接官が明らかに退屈そうになっていたのに、それに気づかず話し続けてしまった反省もあります。それ以来、表情や相槌から「この辺で十分伝わったかな」と空気を読むように努め、適度に区切って「この説明で大丈夫でしょうか?」と確認を入れるようになりました。また、面接官が頷いていたポイントは深掘りし、そうでない話題はあっさり切り上げるなど、その場のリアクションを手がかりに臨機応変なコミュニケーションを心掛けました。その結果、面接官との会話がキャッチボールのようにスムーズになり、反応も好転したと感じます。
採用は“点”ではなく“線”で見ている

企業側が候補者を見るとき、**単発のエピソード(点)ではなく、キャリア全体のストーリー(線)**で評価していると感じます。私はかつて、面接で聞かれた質問に一生懸命答えることばかり意識して、自分のキャリアの一貫性まで気が回っていませんでした。しかし、ある面接官から「あなたのこれまでの経験は一言で言うと何ですか?」と問われ、はっとしました。自分の職歴を俯瞰して共通するテーマを語れなければ、採用側には「この人を採る意味」が伝わらないのだと気付いたのです。
それ以来、職務経歴や自己PRを話すときは、バラバラの点を繋いで線にする意識を持ちました。具体的には、「○○のスキルも△△の経験も、根底にあるのは◇◇に対する情熱です」といった具合に、自分のキャリアに一本筋を通すよう心がけたのです。さらに、応募先の企業で成し遂げたいことを自身のキャリアの延長線上に位置付けて語ることで、面接官に「うちで働く必然性」が伝わりやすくなります。採用側は点の集合ではなく、その人が描くキャリアの流れを見ていますから、ストーリーを意識して語ることが合格への近道だと思います。
採用担当が感じる「惜しい人」とは
面接まで進んだものの最終的に不採用となったとき、自分では「結構うまくいったのになぜ?」と思うことがあります。それは採用担当から見ると「惜しい!」と思われる候補だったのかもしれません。私自身も後から、「もしかすると自分はあの会社にとって惜しい候補止まりだったのでは」と感じた経験があります。
採用担当者の目線で考えると、「惜しい人」にはいくつかパターンがあります。
- 経歴・スキルは申し分ないのに、面接での態度やコミュニケーションに難があったケース
- 人柄や意欲は十分だが、求められる経験や実績があと一歩足りないケース
- 全体的に優秀だが、**希望条件(特に年収)**が折り合わず最終判断で見送られたケース
例えば、最終面接まで進んだ社で「ぜひ一緒に働きたい」と言われつつも年収交渉が難航し、ご縁が流れてしまったという例もあります。このように一部がマッチしないために見送られるのが「惜しい人」の実態です。
では自分が「惜しい人」だった場合、次に活かすにはどうすればいいでしょうか。私は、不採用だった面接については一人反省会を開き、「どこを改善すれば次は受かるか」を考えるようにしました。ときには転職エージェントにフィードバックを求めたり、ChatGPTのようなAIに面接の想定問答を投げて客観的なアドバイスを得たりもしました。自分では気づかなかった弱点を洗い出し、次の面接ではそこを補強する——これを繰り返すことで、「あと一歩」を埋めていけると思います。
本音:最終面接で何が評価されているか?
選考の最後の関門である最終面接。私の経験上、ここでは能力というより熱意とフィット感が評価されていると感じます。最終面接は役員クラスが担当することも多く、判断基準は「この人と一緒に働いたイメージが持てるか」「社風に合いそうか」といった点にシフトします。極端に言えば、即戦力かどうかは一次~二次で見終えており、最後は**「人としてうちにマッチするか」**を見ているのです。
実際、最終面接では雑談に近いリラックスした質問を受けたり、「うちに入ってやりたいことは何?」と率直に熱意だけを確かめられたりする場面が増えます。私が内定をもらえたケースでも、最終では経営者とのざっくばらんな対話を通じて「肩の力を抜いたあなた自身の人柄を知れて良かった」と言われました。逆に言うと、最終まで進んだ複数の候補から誰を選ぶかは、スキルの優劣ではなく「一緒に働きたいかどうか」の直感的な印象で決まる部分も大きいのでしょう。
そして本音を言えば、企業側は条件面のシビアな天秤にもかけています。最終選考まで残った私よりも若く年収希望の低い候補者がいれば、そちらが選ばれることも現実にはありました。それを嘆いても仕方ありません。私たち40代の求職者は、最終面接では**「この人と働きたい」と役員に思わせること**に全力を注ぐしかないのです。
具体的には、会社や仕事への熱意をあらためて真っ直ぐ伝えること、そして条件面で柔軟さを示す準備もしておくことです。私は最終面接前に「この会社で成し遂げたいこと」を明確にし、多少年収が下がっても挑戦したいことがあると伝えられるよう準備しました。その熱意が伝わり、最終的に内定を得ることができました。最終面接は単なる形式ではなく、最後のアピールチャンスです。油断せず人柄と熱意を最大限に示し、「この人なら一緒に働きたい」と思わせることができれば、きっと結果はついてくるでしょう。